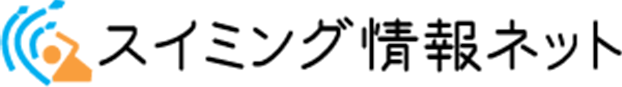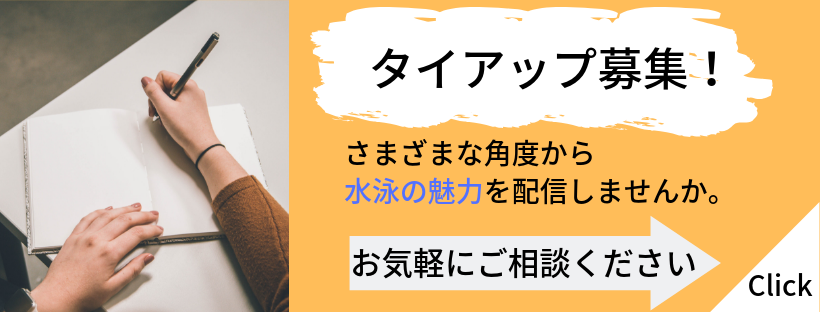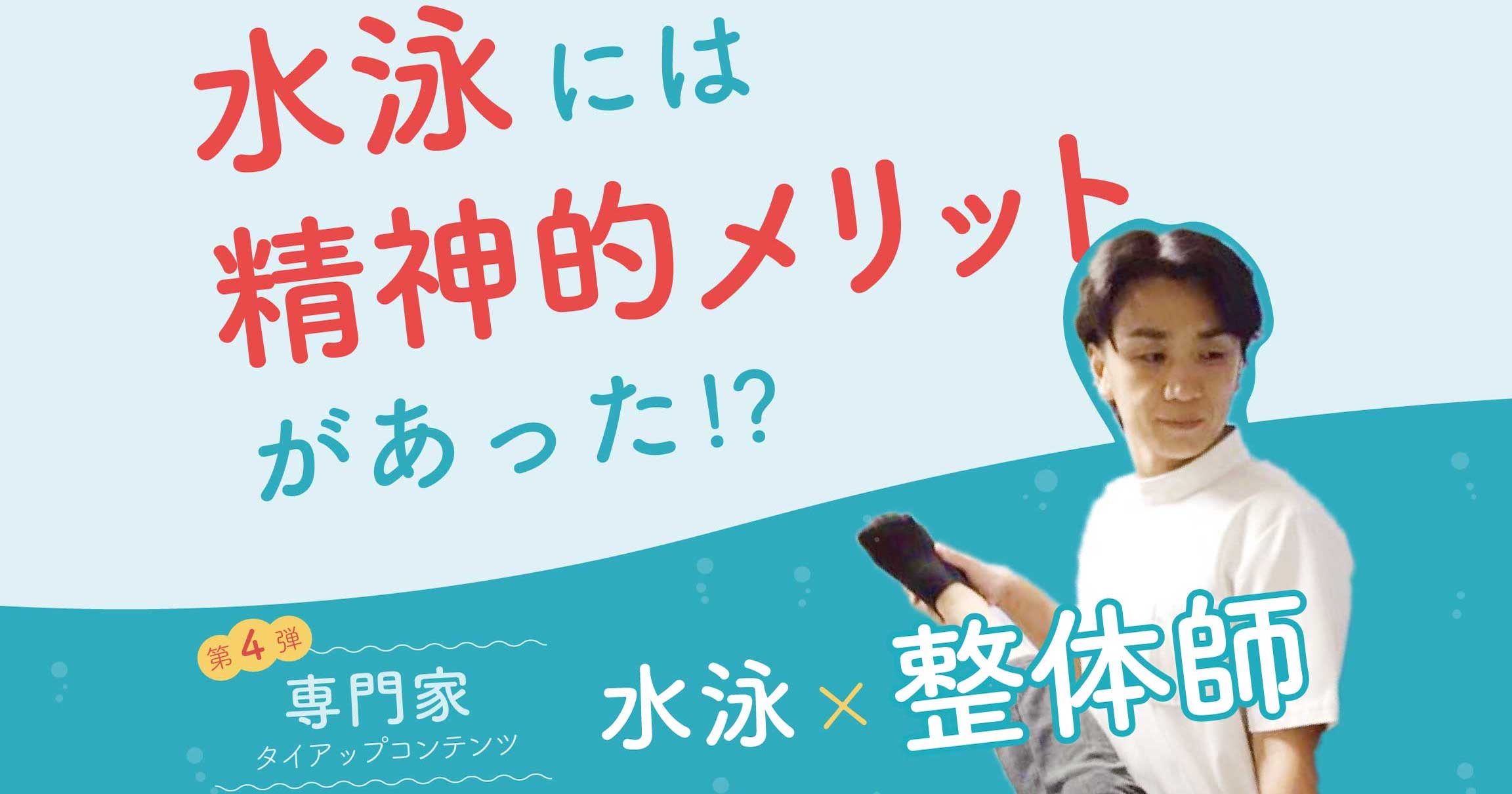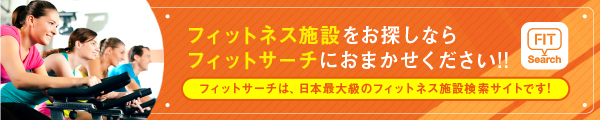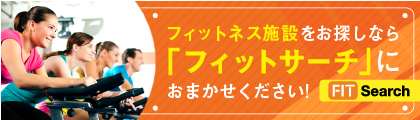赤ちゃんから子供までスイミングに通わせるべき理由とは?【応用理学士が語る】

★この記事をざっくり要約すると!
- 応用理学士の観点から水泳の魅力を紹介
- 現代病の改善に繋がる
- 低年齢から始めて長く続けることでさらに好影響
第3回「専門家タイアップ」コンテンツです。
今回は、「応用理学士・カイロプラクティック理学士」の檜垣暁子さんに、赤ちゃんから子供までスイミングに通わせるべき理由を執筆していただきました。
■略歴
・2000年 オーストラリアロイヤルメルボルン工科大学(日本校5年制)にて応用理学士 取得
・2002年 カイロプラクティック理学士 取得。
・2003年 横浜市にあきカイロプラクティック治療室を開院
・専門家による生活情報サイト「All About」にて肩こり・腰痛記事を執筆。
「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」などでの出演・執筆・監修など。
・日本カイロプラクターズ協会(JAC)正会員
・日本カイロプラクティック登録機構(JCR:Japan Chiropractic Register)登録カイロプラクター
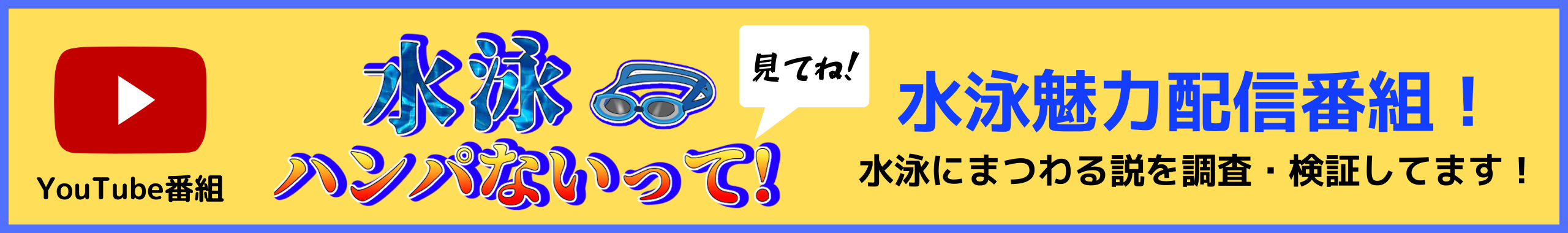
■ポートフォリオ
・「マッサージに通っても肩こりが治らない本当の理由」(秀和システム)
・「今すぐできる!肩こり・首痛を治す32のルール」(学研パブリッシング)
・「自分でできる!腰痛セルフケア」(芸文社)
・「All About」にて肩こり・腰痛
https://allabout.co.jp/gm/gp/51/
・あきカイロプラクティック治療室
http://www12.plala.or.jp/akichiro/
赤ちゃんからスタートできるスイミング
赤ちゃんの頃から始めることができる代表的な習い事のひとつである「スイミング」。
出産して数か月が経ち「わが子がすくすく健康に育つためには……」と考えたときに生後数か月後(スクールにより異なります)から、ベビースイミングを検討する保護者も多いと思います。
また、幼稚園に入園してから、小学校へ入学してからというように年齢が上がってもスイミングスクールは人気です。子供の頃から始めるスイミングのメリットをなんとなく知っていて、その効果を楽しみにスイミングを習わせる、といった声も聞かれます。
スイミングを通して心身が受けるあらゆる刺激によって、体の状態が少しずつ変わっていきますので、幼少の頃からスイミングを始ていたお子さんと、何もしていなかったお子さんとの間にも違いが生じます。
まずは、子供の頃から始めるスイミングがもたらすメリットにも触れながら紹介していきましょう。
1.水に慣れるだけではなく大切なコミュニケーションの場にも

顔に水がかかることが苦手、水深も浅くて小さな子供用プールでも怖がってしまい、近寄ろうともしないというお子さんがいます。顔に水がかかった時に不快な思いをしたのかもしれませんが、日々の入浴も嫌がり時間がかかって毎度苦労するという話も聞きます。
ベビースイミングのように赤ちゃんの頃から親と一緒に水に親しむことで、水が怖いものだと思わないよう慣れることができます。遊びの要素を入れながら楽しむ幼児期のスイミングスクールでも水嫌いを克服できるようカリキュラムが組まれています。
ベビースイミングでは、親が一緒にプールに入り、また幼児の場合はスイミングへ通うために親が付き添ったり「上手にできたね!ちゃんと見てたよ~。」などニコニコ笑顔で声掛けをしたりすることもあるかと思います。特に母親と子の穏やかなコミュニケーションが増えることで、お子さんの脳内では喜び嬉しいなどの感情を司る領域が、刺激され感情の安定性につながることが考えられます。
逆を言うと「まだ水に潜れないの!?」とイライラしながら言葉を言い放つことはマイナスな影響を与えかねません。スイミングを通して我が子との温かみのある会話は、脳の健やかな発育にもプラスの影響を与えるのではないでしょうか。精神の安定性は、成長過程において大切であり、成人してからの健康状態にも影響する場合があります。
2.成人にも多い自律神経の乱れによる体調不良

精神の安定性は「自律神経」の機能にも影響を与えます。
自律神経の中枢は脳の視床下部というところで、自律神経には交感神経と副交感神経があり協調しながら、生命を維持するために体の状態を一定に保つ働きがあります。自律神経が支配するのは、全身の筋肉、血管、分泌腺であり自分の意思とは関係なく働きます。
また、内臓の働きにもかかわります。水が苦手なお子さんがスイミングスクールに通い始めた頃、行く直前になると「お腹が痛い~。」となる場合も「スイミング(水)が怖い、緊張する」といった心の動揺から自律神経の働きに影響を及ぼした結果です。全身の調子に関係のある自律神経ですが、成人になると、多様なストレスにさらされ自律神経の乱れから病気とまではいかない体調不良を訴える人が増えます。
体調不良の例
・体の冷え(お腹やお尻、太ももなど触れると冷たい・手足など末端の冷え)
・低体温気味
・ストレスが胃腸の不調へつながりやすい(食欲不振・便秘・下痢など)
・肩こり、背中の張り、頭痛
・睡眠の問題
・目が疲れやすい
・気持ちが不安定になりやすい
・風邪を引きやすい
スイミングには、この自律神経のバランスを整え心身のコンディションに嬉しい影響を及ぼす可能性が考えられます。
子供の頃からスイミングを続けていくことで、脳への様々な刺激が入り交感神経と副交感神経のバランスを始め免疫系も安定しストレス耐性も向上するようになると、健康的に年齢を重ねることができる可能性が高まります。スイミングをせずに過ごしている子供と比較すると、こういった面でも違いが生じるケースがあると思います。
3.子供のスマホやゲームからの悪影響を軽減させたい

幼児期から、スマホやゲームに接する機会が増え、その間、背が丸まったような悪い姿勢で過ごしがちに。また、目からも過剰な光の刺激が入ったりといつのまにか目を酷使してしまうといったことを心配している保護者の方もいらっしゃいます。また、それ以降の年齢でもタブレットでの勉強やパソコン使用などの機会がますます増えていくと思われます。
重力がかかった状態で、頻繁に悪い姿勢が繰り返されたり長時間に及ぶと、悪い姿勢により負担のかかっている関節からの信号が度々脳へ送られ偏りが生じ、部分的に筋肉の緊張が過度になり、子供ながらに肩こり・頭痛・慢性的な不良姿勢(重心のズレ)を招くことがあります。
ここからも自律神経の乱れに繋がり、大切な成長期に肩こりや首こりで頭がボーっとしたり、筋肉の正常な働きが損なわれ、本来の筋力を発揮できず、疲れやすくなったりするかもしれません。成人になるよりも早期(高校生や大学生など)に、自律神経失調の症状を訴えるケースもあります。
4呼吸機能・体温調節機能も整える
 .
.
また、プールに浸かる際の水圧によって、心拍数や肺活量の変化に伴い呼吸機能が向上していくことが考えられます。ストレスにさらされがちな成人が、難しいと感じることが多い深呼吸。識的に深呼吸をしたり、安定したリズムで呼吸をすることが自律神経の安定にも繋がります。
さらに、水温によるプラス効果も期待できます。寒冷刺激といい皮膚から温度差による刺激が入り体温調節を無意識下で行い自律神経機能が鍛えられます。室内プールの水温が29~31度である場合、体温よりも低いため熱伝導率の大きい水中では体熱が奪われやすいのです。体熱を奪われないよう体温を調整する働きは、自律神経機能だけではなく、免疫機能向上にもつながり、風邪に強い体づくりにも良いといえます。
体温調節機能の正常な働きは、成人してからの「つらい冷え症状」改善にも関わるため、将来の体調不良を減らすためにも、子供の頃からのスイミングは役立つと言えそうです。
5.水中での運動で筋肉を使い硬くならない体づくり
水中では浮力によって関節への負担が軽減されます。目の酷使や悪い姿勢により関節や筋肉へ負担のかかりがちなお子さんは、水中で全身を動かすことで、不調をきたしやすい状態から脱することが必要になります。
水泳では、推進力を得るために腕を大きく動かし水を手でかいたり、下半身では、クロールのキックしたりと、筋肉をしっかり使います。筋肉を使うことで、力を十分発揮できるようになり、関節の可動性も正常に保つことができるでしょう。
また、不良姿勢が続くと、腕を大きく回す際に硬く感じたり、体を動かせる範囲が狭まり動作が重く感じるなど、筋肉の働きが低下する場合があります。子供ながらにコリを招くような血流の滞りにつながると、これもまた自律神経のバランスを崩す要因となります。
6.子供のころからのスイミングで神経機能の向上を
そしてスイミングスクールに子供の頃から通うお子さんは、定期的にカリキュラムをこなすことで全身運動を低年齢から続けていくことになります。水中で体のどの部分をどのくらい、どのように動かしたら理想的な泳ぎ方になるのか、速く泳げるのかなど脳内で思考し運動の計画をたてて、それを最適に近い動かし方へ微調整しながら「自分の理想の泳ぎ」へ発展させるといった複雑なことを神経の働きを通して実行しています。
スイミングスクールで先生の指示を聞き理解しようとすること・泳ぐ練習を重ねることなどにより脳も活性化され、発達に大切な神経機能の向上と安定性に繋がっていくと考えられます。
低年齢から始めて長く続けたいスイミング
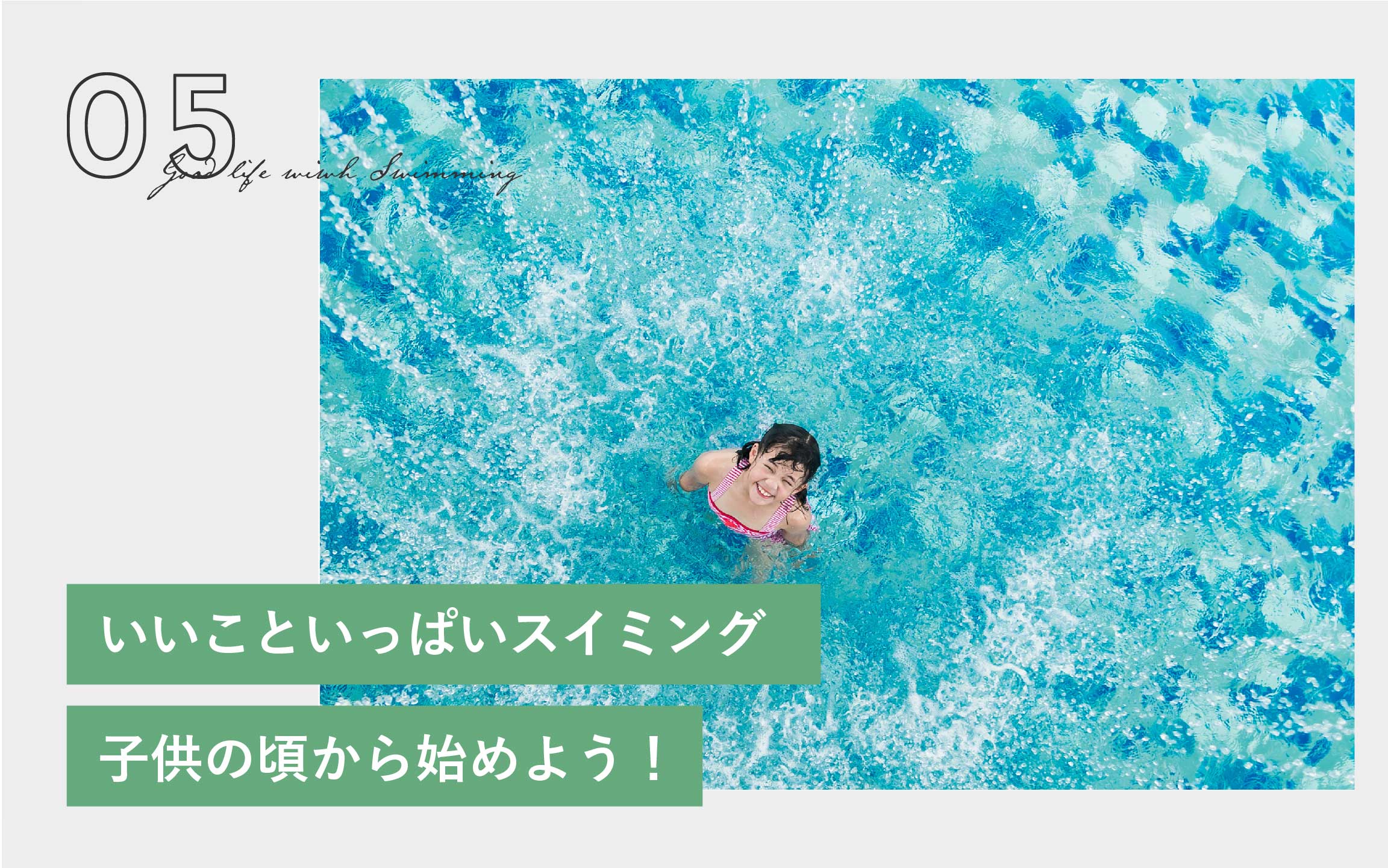
ベビースイミング・幼児期のスイミング・就学してからのスイミングと年齢やその子供のレベルにより組まれるカリキュラムは異なりますが、子供の頃からスイミングを続けていくことで、水中だからこそのメリットのもと、脳へ様々な刺激が伝わり心身の発育にも良いものであることが想像できましたでしょうか。
得られた達成感は自信にもつながります。子供の頃からスイミングを始めるメリットを将来へ生かしていただきたいと思います。
※本記事の監修メンバー
・水泳歴20年のアドバイザー「渡邉氏」
・あきカイロプラクティック治療室の「檜垣氏」
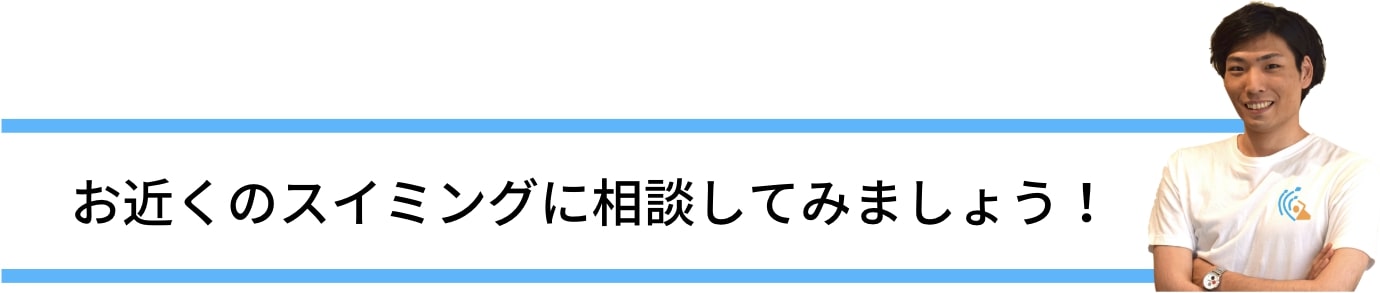
p.s.
「スイミング情報ネット」では
各専門家様とさまざまな角度から水泳の魅力をお届けする、
「専門家タイアップ」コンテンツを配信しております。
水泳の魅力を伝えたい専門家様、お気軽にご相談ください!